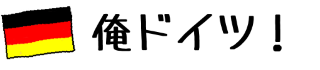ドイツでは、大戦について論じることは時にタブーな部分があります。一方で、先人の過ちや失敗を通じ、新たな教訓が得られることもできますので、それについて知ること自体が問題なのではなく、公的な場で論じることが問題になるということを知っておいてください。
スポンサーリンク
ナチスドイツのアフリカ遠征
第二次世界大戦は、文字通りオーストラリアからユーラシア、アフリカまで世界のほぼ全土を巻き込んだ大戦だったわけで、実際に連合軍、枢軸軍ともにアフリカでも多大な犠牲を出しています。なぜドイツ軍がこんな辺鄙で不毛な戦いに巻き込まれたかというと、同じ枢軸国の仲間であるムッソリーニが、往年のローマ帝国再興を夢見て、アフリカ侵攻を始めたことと、イギリス本土侵略をたくらむヒトラーの思惑がある程度一致したからで、事の起こりは、アフリカのイタリア軍がエジプトのイギリス軍を攻撃したことでした。
総力戦ですので、本土に直接被害が無くとも、植民地を失陥すると大英帝国としてはかなり手痛い犠牲をこうむります。同じ考えでナチドイツは日本にイギリスの植民地であるインド攻撃も要請していますが、利害関係がかみ合わずに不発に終わりました。
Im September 1940 eröffneten italienische Streitkräfte von ihrem libyschen Kolonialgebiet aus eine Offensive gegen das unter britischer Herrschaft stehende Ägypten. Eine Ende des Jahres begonnene Gegenoffensive führte die Briten bis Anfang Februar 1941 nach El Agheila an der Großen Syrte. Gleichzeitig gingen die italienischen Kolonien in Ostafrika an britische Truppen verloren.
『1940年、リビアの植民地に駐留していたイタリア軍が、エジプトのイギリス常設軍に対して攻撃を開始したが、年末から1941年の初めにかけて、イギリス軍のエルアラメインへの反撃が激化した。同時に、東アフリカのイタリア植民地軍はイギリス軍の前に敗北を始めた』
ローマ帝国の再興というと聞こえはいいですが(というか、ISISみたいですが)、実際のところイタリアもドイツもイギリスやフランスの植民地獲得戦争に遅れたため、イタリアもアフリカの植民地がほしかった、というのが本音です。
ただし、イタリア軍の機械化は第二次世界大戦開戦当時、十分に間に合っていません。1930年代に国際的な反発を買いながらイタリアはエチオピアを植民地化しますが、ここでも原始的なエチオピア軍相手に割と大きな犠牲を出しています。ムッソリーニも、大戦の開戦はもう少しあとだと思っていたふしがあるようで、1940年の状況でも、師団の機械化は進められていませんでした。
よって、兵数では現地のイギリス軍を圧倒しながらも、イタリア軍の古風な戦術と兵器では、もともとイギリス軍との戦いにはなりえませんし、日本軍同様、イタリア軍も砂漠という過酷な環境下で兵站を無視した戦いを続けます。最初のうちは、数の暴力に任せてイギリス軍の都市を占領しますが、今度は戦車や弾薬などの補給をふんだんに受けたイギリス軍に包囲され、10万以上の捕虜を出す大敗を喫します。
そうすると、今度はドイツ軍は困ります。ドイツ軍にとっては、イタリア軍が何人死のうが構わなかったと思いますが、イタリアが連合軍に降伏すると、ドイツは地中海から挟み撃ちにあうことになり、これは非常に良くないです。というわけで、すでに西へ東へ大きな兵力を割いていたドイツ軍ですが、アフリカにも兵を派遣しなければならない羽目になりました。ここで、かの有名なエルヴィン・ロンメルが登場します。
砂漠のキツネ、ロンメル師団
そもそもロンメルは、エリート階級の出身者ではありませんでした。最終的に、元帥まで上り詰めることとなりますが、これは極めて異例のことです。彼は今でも連合国、枢軸国問わず多くの人の尊敬を集めていますが、それは、彼が最後まで騎士道を貫いて、ヒトラー暗殺事件の首謀者に甘んじたことや、このように貴族以外から上り詰めた経歴があるからです。
第一次世界大戦に従軍したのち、フランスなどの過酷な軍縮のなか、10万人のドイツ兵の中に残ることが決定されます。その後、ヒトラーの寵愛を次第に受けるようになり、ロンメルは出世への道を進みます。
第二次世界大戦勃発後は、東へ西へ従軍し、たびたび命令を無視しながらも戦果をあげ、ヒトラーの子飼いの将軍として活躍しました。その彼が、1941年2月、満を持してこの過酷なアフリカ戦線に派遣されてきたというわけです。
 ここから、ロンメルの破竹の勢いが始まります。元々補給の限られた戦いの中、ロンメルはあの手この手を使ってイギリス軍を困惑させます。有名どころですと、張りぼての戦車を作ってそれを見たイギリス軍を撤退させたり、兵器が限られているのでイギリス軍の弾薬や戦車を上手く鹵獲して使ったり、などです。
ここから、ロンメルの破竹の勢いが始まります。元々補給の限られた戦いの中、ロンメルはあの手この手を使ってイギリス軍を困惑させます。有名どころですと、張りぼての戦車を作ってそれを見たイギリス軍を撤退させたり、兵器が限られているのでイギリス軍の弾薬や戦車を上手く鹵獲して使ったり、などです。
そうした天才的な戦術眼もあり、一時的にアフリカ戦線はドイツ軍の形成有利に進みます。特に、北アフリカを舞台としたガザラの戦いでは、イギリス軍の半数近い戦車しか持たなかったにもかかわらず、イギリス軍を破る戦いを見せています。
こうした『寡兵で大軍を破る』という戦い方には、大勢の人々が魅了されるものです。カンネーの戦いしかり、三国志の赤壁の戦いしかり、織田信長の桶狭間しかり、かくも見事に形勢不利な状況から大軍を蹴散らすとさも気持ちよく見栄えしますが、それらは基本的にイレギュラーで、戦争は数と兵器の質で決まります。もう少しいうと、いくら局地戦で勝っていても、大局的に敗北するとどうしようもありません。
というわけで、各地の戦い自体では時にドイツ軍有利に進められていたのですが、結局、慢性的な兵器不足はどうしようもなく、じりじりと連合軍に押されていくこととなります。この点は、太平洋の日本軍に関しても同じことで、もともと空母の建造量が限られている日本軍は、強大なアメリカを相手に、勝つのではなく、無傷で勝つことを強いられます。そうしないと、いくらこちらと相手との損害比が1:2だったとしても、生産比率が1:10である以上、いずれ敗れ去るはめになるからです。
というわけで、アメリカが連合軍についた時点で、この戦いには無理がありました。結局、アフリカのドイツ軍は東西からアメリカ軍のふんだんな補給を受けた連合軍に挟撃される形で敗れ去り、アフリカ戦線における戦いは幕を閉じます。
結局、ナチスドイツはアフリカでほぼ一つも得るものが無く、兵士たちは捕虜になったり西部戦線に転戦したりし、アフリカ戦線で活躍したロンメルもノルマンディーに転戦し、最終的にはヒトラー暗殺計画への関与を疑われて自死を賜っています。
余談ですが、日本の潜水艦がフランス軍と結託してマダガスカルを攻撃したりもしてますが、こちらも戦略的にはなにも得るものがなかったようです。結局のところ、いくら兵士が優秀であろうと、いかに局地戦で勝ち進もうとも、全体的に戦略的に見て破れてしまえば、それでおしまいです。