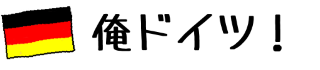ドイツは、戦火の中から生まれた帝国でした。普墺戦争、普仏戦争と、近隣の大国を破り国際的な地位を向上させ、遅咲きながら欧米列強の仲間入りを果たしたわけです。
にもかかわらず、ビスマルクは冷静でした。プロイセンが戦争に強いからと言って、かつてのナポレオンのように周囲をすべて敵にまわしてしまってはどうしようもないことを知っていたのです。
そんなビスマルクが心血を注いで築き上げたのが「ビスマルク体制」ですが、1888年にヴィルヘルム2世が即位すると、このビスマルク体制がヨーロッパの平和もろともがらがらと音を立てて崩れていきます。
ビスマルク政権下でのドイツ
スポンサーリンク
ヴィルヘルム2世の即位とビスマルクの失脚
1888年当時、ビスマルクは国内の社会主義者を取り締まる「社会主義者鎮圧法」を熱心に行っていました。上述のように、ビスマルクの関心は欧州国家と強調してフランスを封じ込め、もっか海外領土の獲得にはあまり積極的ではなく、内政の基盤を整えることのほうが優先順位が高かったのです。
一方、ヴィルヘルム2世の戦略眼は違いました。当時統一されたばかりのドイツには、イギリスやフランスのような海外植民地がありません。イギリスはアフリカ、インド、オセアニア、北アメリカなど世界をまたにかけた植民地帝国を保持し、フランスも同じように当時、東南アジアやアフリカに広大な版図を築いていました。
(写真出典ウィキペディア)
ここに至り、帝国主義を促進したいヴィルヘルム2世と慎重派のビスマルクの間に軋轢が生まれたのです。そんな中、上述の「社会主義者鎮圧法」は、ビスマルクを更迭するのにうってつけの理由でした。
Ich will meine ersten Regierungsjahre nicht mit dem Blut meiner Untertanen färben
「私は国王としての初年を臣民の血で彩るようなことはしたくない」
ヴィルヘルム2世は体のよいことを言って、ビスマルクの国策を非難します。最終的にビスマルクは失脚、ドイツの政治舞台から姿を消し、この期を境に、ドイツは狂信的な領土拡張と帝国主義のレールを進み始めるのです。幸か不幸か、失脚したビスマルクは1898年、ドイツの破滅的な将来を目にすることなく病没します。
(写真出典ウィキペディア)
ヴィルヘルム2世の世界政策
ヴィルヘルム2世は外交的な失敗をしましたが、その彼が推進した帝国主義が善であったか悪であったかの倫理的な視点から論じるのはお門違いです。当時、イギリスもフランスも強大な植民地帝国を抱えており、これにドイツが便乗したからと言って、決してドイツだけを責められるものではありません。
これは、第二次世界大戦前の日本にも言えることですが、これを植民地支配は是か非か、という倫理的な観点から論じることは難しいです。その代わり、外交的な観点から論じるのであれば「他国の利益を損ないかねない」行動をしはじめた、とは言えます。他国とは何でしょう。当時最大の植民地帝国を保持するイギリスやフランス、そしてバルカン半島の権益を狙うロシアです。
ドイツが植民地を拡大することで、こうした国たちの国益を損なう恐れが出てきました。これは、今までフランスを封じ込めるためにドイツと強調していた国たちが、次第に反ドイツに傾いていく原因になります。
ビスマルク体制の綻びは、まずロシアから訪れました。1890年に失効する独露再保障条約の更新をドイツ側が拒否したため、ロシアはフランスと接近、ビスマルクの最も恐れていた東西から大国に囲まれる、という状況にビスマルク失脚後即座に置かれてしまったのです。
このころロシアとイギリスは東アジアの覇権をめぐって仲たがいしていたころですので、敵の敵は味方、理論でドイツはイギリスに接近します。ただし、上述のようにヴィルヘルム2世の帝国主義は、はなからイギリスと対峙するような未来を孕む性格のものでした。
例えば、東アジアに目を向けると、1897年、ドイツ人宣教師が清で殺害されたことを口実に、ドイツは清から膠州湾の租借権を獲得します。清はこのころ、日清戦争で破れたことから国際的な地位が低下、欧米列強の食い物にされている真っ最中で、ドイツもその一人でした。ただ、イギリスからしてみたら、東アジアの利権にドイツが絡んでくるのは当然面白くありません。
中東問題はさらに緊迫していました。ドイツは、近代化の波に乗ることができず、国際的な地位を低下させ続けてきた欧州の「瀕死の病人」であるオスマントルコ、そしてオーストリアと接近し、バルカン半島方面への版図拡大を狙い始めたのです。
この中東への接近は、ベルリン、ビザンティン、バグダードを結ぶ鉄道網を敷設し、ペルシャ湾の利権をドイツが獲得しよう、というのが狙い(3B政策)でしたが、当然のことながら、バルカン半島を狙うロシアや、イギリスの3C政策を脅かすこととなり、彼らの不興を買います。
こうすると、今度は欧米列強は反ドイツの流れに傾いていきます。ドイツの台頭は、彼らの将来的な利権の妨げになりかねません。いつの間にか、ビスマルクの築いたビスマルク体制は崩壊し、19世紀の終わるころには、ドイツは欧米列強間で孤立するようになっていました。
そんな中、ヴィルヘルム2世が「黄禍論」を唱え、日本人を敵視したのは納得できます。とりあえず、四方に敵を作る状況はまずいので、ヨーロッパの外に共通の敵を作ろう、という算段です。
黄禍論とロシアへの接近
黄禍論は、もともと日本人だけではなく、黄色人種全体を対象にしたものです。ただ、政治利用にあって、国力の大きい中国と、急激に力をつけ始めた日本を対象に攻撃するようになりました。ヴィルヘルム2世が本当に黄禍論の信奉者だったのか、それとも政治利用しただけだったのかは知りませんが、ヴィルヘルム2世はこの「黄禍論」を口実に、ロシアのニコライ2世と急接近を果たします。
「ヨーロッパの国民諸君、汝の神聖な財産を守り給え!」
例えば、上の絵は、ヴィルヘルム2世が同じ白人国家同士で結託し、黄色いアジア人をやっつけよう!というコンセプトのもとに書かれた絵です。また、ヴィルヘルム2世は義和団事件の際などは「フン族演説」を行い、中国人に対して一切の手心を加えずに征服せよ、というような主旨の演説を行うなど、だんだん黄禍論運動に意欲的になっていきました。
ニコライ2世も、だんだんその気になってきます。ニコライ2世はヴィルヘルム2世の従兄弟の間柄でもあり、もともとつながりがありました。ヴィルヘルムは手紙をしたため、ロシアこそがアジアで悪の黄色人種から、われらが白色人種を守るための救世主となるのだ、と大げさに褒めたたえています。
ロシアは、かつてタタールのくびきと呼ばれるモンゴル人(黄色人種)の支配を受けており、黄色人種によいイメージは持っていません。こうした歴史的背景を利用し、ヴィルヘルム2世は、ロシア皇帝ニコライ2世の目線を、バルカン半島から東アジアに向けさせることに成功したのです。
(おまけに、ニコライ2世は大津事件で日本人に襲撃され、頭部に重傷を負っており、特に日本人には嫌な思い出があります)。
さて、ヴィルヘルム2世はうまくロシアの目線をアジアに向けさせることに成功しましたが、この動きを黙って見過ごすわけにはいかない勢力があります。当時最強の海軍を抱え、世界中に植民地を保持していたイギリスです。これ以上アジアでロシアの勢力が台頭してしまうと、自分たちの利権が食いつぶされかねません。
そんなわけで、ドイツ・ロシアvsイギリス・日本、という外交の背景が、日露戦争前までに形成されていきました。
この極東の戦争の帰趨が、のちのヨーロッパに重要な影響を与えることになります。